
(この記事は、2024年9月30日に配信しました第406号のメールマガジンに掲載されたものです)
今回は、クロード・ドビュッシーのお話です。
クラシックTVというテレビ番組で、クロード・ドビュッシーを取り上げていたので見てみました。司会者の清塚さんがアレンジしたドビュッシー作曲「月の光」のピアノ演奏で、番組はスタートしました。
番組ゲストは女優の成海璃子さんで、映画でピアニスト役をされていた時に、ピアノの指導が清塚さんだったという関係があるそうです。大の音楽好きと紹介されていました。成海さんは、5歳くらいからピアノを習っていたそうですが、数年で止めてしまい、その後はピアノを弾く機会がなかったそうです。しかし、コロナが流行した時にピアノを再開し、ラグタイムを練習しているという成海さんに、清塚さんが「え~っ!」と言って、ちょっと話が盛り上がっていました。ラグタイムは19世紀末頃、北アメリカで生み出された黒人音楽に影響を受けた音楽ジャンルで、スコット・ジョブリン作曲の「エンターテイナー」がとても有名な作品です。清塚さんがラグタイムもクラシックに取り入れたのは、ドビュッシーではないかという話をしますと、もう一人の司会者で歌手・モデルの鈴木愛理さんと成海さんがとてもびっくりしていました。
ドビュッシーの印象について、成海さんは、「テレビやコマーシャルで何回も聴いたことがある有名な曲ばかりで、有名な曲が多くて聴き覚えのある曲ばかりだなあという印象がある」と答えていました。
番組では、ドビュッシーの代表曲として「ベルガマスク組曲」から「月の光」のピアノ演奏を見ながら、「メロディーとも言えないような音楽で、口ずさむような音楽でもないし、不思議な感じがする音楽ですね」と清塚さんが解説していました。確かに、ベートーヴェンやモーツァルトのように覚えやすいメロディーという訳ではないですね。また、ハープ演奏で「アラベスク第1番」、ピアノ演奏で「亜麻色の髪の乙女」が流れますと、「美術館に行っているような気分がしますね」という解説や「天才だなっと思いますね」という感想も出てきていました。
ドビュッシーがどんな作曲家なのかという質問に、清塚さんは、とても困っている表情を浮かべつつ、「一言で説明するのは難しいよ。だけど、テレビだから仕方なく一言でいうと、音楽で絵を描いた人」と答えていました。司会の鈴木さんが、笑いながら直ぐに「えっ、どういうことですか?」と聞き返し、成海さんは、「絵を描く?!」と不思議そうな表情を浮かべていました。確かに、「?」と思う方も多いかもしれません。「音楽を鑑賞しているというより、映像を観ているような気分に不思議となっていますよね。ビジョンやイメージで、絵を音で描くところが、ドビュッシーのすごいところだなあと思いますね」という清塚さんの言葉に、「うん、映像が浮かんできますよね」「目を閉じたくなる感じ」と鈴木さんも成海さんも頷きながら感想を話していました。
ドビュッシーは、1862年にパリ近郊の町で生まれましたが、この頃のパリは経済的にも政治的にも不安定だったそうです。ドビュッシー家の生活も影響を受けていたようです。ドビュッシーは内気で不愛想な性格だったそうで、番組では幼少期のドビュッシーの写真も紹介されていましたが、少し気難しそうな雰囲気でした。学校帰りに、同級生が安いお菓子を一杯買って、ほおばる中、ドビュッシーはおしゃれなパイやキャンディーを少量だけ買うような子供だったそうです。
ドビュッシーに運命の転機が訪れたのは、カンヌに住む叔母の家を訪れた時です。そこで、これまで触れたことがないピアノに出会い、叔母がコレクションしていた絵画なども初めて目にし、ドビュッシーは大きな感銘を受けたそうです。そして、パリに戻ると、ピアノを始めてわずか10ヵ月でパリ国立高等音楽院に入学したそうです。すごい天才ぶりですね。しかし、気難しい性格だったために音楽院に馴染むことができず、友達も音楽家ではなく別のジャンルの人ばかりだったそうです。叔母の影響で目覚めた美術への興味と、音楽以外の交友関係がドビュッシーの音楽に重要なものだったようです。
番組では、ドビュッシーの交友関係をまとめて紹介していましたが、特に美術界では、ドガ、ルノワール、ドニ、ロダンなどの名前が挙がっていました。有名人ばかりで驚きますね。この頃のパリは、芸術家たちが集まっていた時代で、カフェで朝から晩までずっと芸術談義をみんなでしていたそうです。成海さんに交友関係について聞きますと、「ミュージシャンの方で、仲良くさせてもらっている人が多いですね」と答えていました。直ぐに、「じゃあ、女優仲間はそんなにいないの?」と冗談で聞くと、成海さんは大笑いしながら「うん」と頷いていて笑いが起きていました。「ドビュッシーと一緒だね」「別のジャンルの友達が多いんですよね。なんでですかね」と成海さん自身も驚いていました。「別のジャンルの方のお話を聞いている方が、勉強になったりするよね」「なんかわかる気がしますね。違うところからもらう感性の方が、吸収できたりしますよね」と話がどんどん盛り上がっていました。
番組では、ドビュッシーの音楽と絵画の深い関係について、当時ドビュッシーが出版した楽譜の表紙を3つを紹介していました。
1つ目は「選ばれた乙女」という作品の楽譜で、この作品自体も絵画から着想されたもので、画家のドニに表紙の絵を発注する程こだわりがあったようです。2つ目は「交響詩 海」という作品の楽譜で、日本の浮世絵を表紙に使っています。ドビュッシーは、自分の書斎にも同じ浮世絵である葛飾北斎の作品を飾ってました。3つ目は、「子供の領分」という作品の楽譜で、この表紙はなんとドビュッシー自身が描いたのだそうです。この「子供の領分」の作品の中にも、成海さんが練習しているラグタイムの音楽に通じるものがあるという感想も飛び出していました。
「楽譜の表紙にもこだわるという点でも、ドビュッシーの美的感覚と、絵で作品の内容を象徴している事がわかりますね」という清塚さんの解説に、成海さんも頷いていました。絵画と曲が強く結びついているドビュッシーは、異国への興味も持ち合わせていました。先程紹介した書斎に浮世絵を飾るだけでなく、仏像まで所有していたそうで、エキゾチックな要素を自身の作曲に取り入れていました。例えば、「金色の魚」という作品は、日本の絵画で、金で描かれた魚から影響を受けたそうですし、「アラベスク第1番」は、イスラム美術のアラベスク模様から着想を得て作曲したのだそうです。
番組では、いろいろな文化を音楽に取り込んでいる異国情緒を投影している部分を、清塚さんが生演奏しながら紹介していました。「アラベスク第1番」では、曲線が連なるアラベスク模様を作品で表していて、清塚さんの演奏を聴いて「出口のない感じ」「糸を巻いているような感じ」「細い感じ」と次々と成海さんと鈴木さんが感想を話していました。
「塔」という作品は、パリ万博でドビュッシーがインドネシア・ジャワのガムラン音楽に感銘を受けて作られた作品です。番組では、なんとドビュッシーがパリ万博で聴いたとされる「クボギロ」という作品を生演奏で披露していました。初めて聴きましたが、音楽の雰囲気が「塔」のピアノ曲の雰囲気に通じるものがあるなあと感じました。とても癒される音色でした。ガムラン音楽の演奏者が、使用された楽器についても解説していました。青銅という金属で作られた楽器で、ひとつずつの楽器の調律をわざと微妙にずらしていて、それによって全体の余韻に「うねり」を生み出しているのだそうです。「そのうねりが、西洋音楽には無いエキゾチックさを生みますよね」と清塚さんも感心しながら感想を話していました。「高音で細やかに旋律を描き、時々低音でゴーンという名前の大きな鐘のような楽器を叩くのを、この様に表現しているのではないか」と、清塚さんがお話しながら演奏していました。「これを聴くと、確かにガムラン音楽を表そうとしていることがわかりますね」と話をしていて、私も頷いてしまいました。
「亜麻色の髪の乙女」や「雨の庭」についても、清塚さんは以下の様に語っていました。
「亜麻色の髪の乙女の冒頭のように、メロディーでもあり和音でもあるものが一本に繋がり、それが細くなびいている感じがして、行ったり来たりしている様子も情景が浮かびます。この冒頭部分を聴くだけで、あたたかい色に包まれた絵画で、繊細で美しい方がたたずんでいる様子が、共通のイメージとして浮かびますね。これがドビュッシーのすごいところなんだよね」
「版画という組曲の中に「雨の庭」という曲があるのですが、結構雨が降っている感じで、床にたたきつけるような雨の感じで、絵画でいうと、土とか床に雨が降っている一瞬の様子を表していて、マイナーな和音を使って、同じ音を連打で使う感じが、バタバタとした躍動感を感じて、音楽でビジョンを表現していて、すごいね」
「絵画を観るときの感覚までをも音楽で表現していて、まさにデザインや絵を描くように音を配置していて、これまでになかった作曲方法を使用して、音楽でイメージを与えてくれていて、こういう和音やリズムの作り方がジャズやロックやポップスにも影響を与えたんですね」と清塚さんが熱く語ると、成海さんも「ドビュッシーって偉大ですね。ピアノという楽器で、ここまで表現できる、表現の可能性に刺激を受けた」と感想を話していました。
西洋の音楽に、東洋の音楽を取り入れたり、絵画的な要素を取り込んで新しい音楽作りをしたドビュッシーの素晴らしさを改めて感じた番組でした。

(この記事は、2024年9月16日に配信しました第405号のメールマガジンに掲載されたものです)
今回は、ピアニストという仕事についてのお話です。
世の中にはいろいろな仕事がありますが、ピアノが好きなお子様の場合、ピアニストに憧れることもあると思います。自分自身のことを振り返ってみても、華やかなドレスを着て、オーケストラとフルコンサートピアノで共演しているピアニストを見て、ピアニストに憧れたものです。しかし、ピアニストが、リサイタルでの演奏以外に何をしているのか、お子様にとってはなかなかイメージが湧かないと思います。
ちょうど、ピアニストにインタビューしている記事がありましたので、読んでみました。インタビューを受けたのは嘉屋翔太さんというピアニストで、2021年にフランツ・リスト国際ピアノコンクールで最高位を獲得されています。3歳の頃にヤマハ音楽教室で先生がピアノを弾いている姿を見て、「カッコいい。自分もピアノを弾きたい」と思ったことがピアニストになったきっかけだそうです。
開成中学・高校生の時にも、ピアノのコンクールで相次いで好成績を収め、高校2年生の時には、コンクールで上位入賞することが出来たらピアニストを目指すため音大受験をすると決めたのだそうです。当時のピアノの先生からは、ピアニストとして活躍できる人は限られ、狭き門であると伝えられていたそうですが、猛練習をして東京音大のピアノ演奏家コース・エクセレンスに特待生として入学することになったのだそうです。
インタビューでは、ピアニストの仕事について「演奏活動」と「練習」を挙げています。演奏活動のために練習は欠かせません。観客の皆さんにはステージで披露する演奏しか見えていませんが、その裏には日々の地道な準備や練習があると話されています。
「演奏活動」には、月に2、3回のコンサートがあり、多くが依頼されたもので早ければ1年前から、急な依頼だと1、2か月前に依頼が来るそうです。コンサートの形態は様々で、ソロのこともあればアンサンブルもあり、会場がサロンのこともあれば個人のパーティーという事もあるそうです。演奏曲目は、リサイタルの場合、自分でテーマを決めて自由に選ぶこともあれば、主催者から希望がある場合には意向に沿うような曲目にするそうです。どちらにしても、特定の時代の作品を選んだり、友人関係師弟関係、相互的な影響を受けた曲を選び、演奏会が終わった時にお客さんの教養が一つ増えるような、お客さんにとって新しい発見や学びが得られるようなプログラムを心がけているのだそうです。確かに、リサイタルやコンサートに行こうと思った時には、誰が演奏するのか、どんな曲を演奏するのかをチェックして選びますよね。ピアニストは、そういうところにも気を配っているのですね。
コンサートに関わる打ち合わせやスケジュール管理、衣装の準備などは全てピアニスト本人が行うそうで、コンサート用のチラシを作ったり、プロモーションもピアニスト自身で行っている方もいるのだそうです。
記事では、具体的に1日のスケジュールも書かれていました。午前中に2時間ほど楽譜の背景などを調べ、午後に2時間半ほど大学院でレッスンを受け、夜に4時間ほど楽譜の全体像を細かく見ながらピアノの練習をしているのだそうです。単に指の練習のためにピアノを弾くのではなく、音楽の構造を理解することを大切にしているそうです。楽曲は、起承転結のある物語のように書かれているものが殆どなので、楽譜の全体像を細かく見ることが大切ですし、一方で音楽には表現をつけることも大切なので、作曲家や作曲当時の時代背景などの調べ物をする時間も、仕事の時間として確保しているのだそうです。また、大学院のレッスンでは、自己練習でまとめたものを先生と共有して、ディスカッションするのだそうです。自分の思い描いた音楽と伝統的な解釈に、大きな隔たりがないのかを確認して、新たな解釈を吹き込む可能性を探るためなのだそうです。
ピアニストのお仕事でのやりがいや苦労についてというテーマでは、指を滑らかに動かすような、ピアノを弾く技術を磨く職人的な側面と、楽曲の魅力を独自に解釈をして表現するという芸術的な側面があることや、音楽には正解がないのが苦労する点ですが、同時にやりがいも感じていると話していました。正解がない音楽の世界では、日常生活で感じる全てのことが演奏のインスピレーションの源になっているのだそうです。
ピアニストになるために、どのようなことを学んだのかというテーマでは、「演奏面」と「対外的な面」という2つの軸で努力をしたそうです。「演奏面」では、ピアノはただ指先で弾くものではなく、耳を使って弾くものだということに気づいたそうです。派手で指をたくさん動かす超絶技巧の曲を弾くのが好きで、そういう曲を弾く自分に酔いしれていた側面もあったそうですが、先生に「何も内容が無い」と指摘されたそうです。ただ音を出すだけなら練習すれば多くの人ができますが、少ない音でいかに人の心を動かせるのかがプロのピアニストだと気づいたのだそうです。そのため、本当に美しいのかと審美眼を養うために、一音一音をじっくり聴きながら弾く練習に切り替えたそうです。バランスよく響いているのか、本当に自分は、ちゃんと音が聴こえていたのかと立ち止まりながら練習をしていて、自分の演奏が変わってきたと思えるまで、1、2年かかったそうです。
対外的な面では、「ピアニストの肩書を得ること」「演奏の機会を増やすための人脈づくり」という2つのことを努力したそうです。大学の特待生になって、演奏の仕事を得られるようにはなったそうですが、やはりフランツ・リスト国際ピアノコンクールで入賞してからの方が、箔が付くので圧倒的に演奏の仕事が増えたそうです。ピアニストとして仕事をするには、第3者から認められる必要があるのですね。
もう一つの「演奏の機会を増やすための人脈づくり」では、演奏の機会を得るために、コンサートを主宰されている方との関係作りを行ったそうです。マネジメント会社との契約をした今でも、以前のお付き合いから仕事の機会を得ることがあるのだそうです。ピアニストは人間関係が重要な仕事なので、礼儀やコミュニケーションの積み重ねを大切にしてきたそうで、演奏の仕事をいただく際にも役立っているそうです。
将来の夢や目標については、クラシック音楽本来の楽しみ方を伝えられるような活動をしていきたいとお話ししていました。クラシック音楽は単に古いという意味ではなく、本来は「一流の」という意味のラテン語が由来だそうです。クラシックを新鮮なもの、廃れないもの、洗礼されたものとして、その価値を広めるような活動をしたいという意気込みも話していました。また、伝統的なクラシックのスタイルを持ちつつ、新しさも兼ね備えることがクラシック音楽界に必要なことと考えていて、将来的にはそのような曲を自ら書いて発表していきたいとも話していました。クラシック音楽の素晴らしさを次の世代に伝えることにも意欲があり、音楽も勉強もどちらも学べるような教室の構想もお持ちなのだそうです。
最後に、お子様の保護者に向けたメッセージとして、人生の中で本気で何かを成し遂げなければならない局面が訪れると思うので、お子様が何かに挑戦したいことがある場合には、環境が許すのであれば挑戦できるようにしてほしいと話していました。ご自身の経験として、かつて一緒に学んだ友人達から刺激を受けることが多々あるそうですし、またご両親が音楽にあまり詳しくはなかったそうで、理解が得られずよく喧嘩もしていたそうです。よくお子様と対話して、お互いの理解を深めることが大切ですし、また、お子様はどこかで保護者を喜ばせたいと思っているものなので、些細なことでもよいので愛情を伝えたら、お子様の頑張りの原動力になるのではともお話しされていました。
ピアニストの普段の生活ぶりなどは、まず知る機会がありませんので、とても興味深く読みましたし、お子様への接し方などについても、学ぶことの多い内容でした。併せて、今後の嘉屋翔太さんのご活躍にも注目していきたいと思いました。
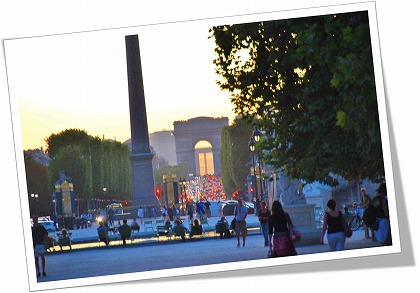
(この記事は、2024年8月5日に配信しました第403号のメールマガジンに掲載されたものです)
今回は、「パリだからこそ生まれた名曲」のお話です。
先日から、パリでオリンピックが開催されていますね。日本選手の活躍が連日報道されています。スポーツは全般的に10代から20代くらいの若手が有利な印象を受けますが、先日の馬術では、40代の選手たちが総合馬術団体で銅メダルを獲得して話題になりました。92年ぶりにメダルを獲得したそうで、まさに快挙なのではないでしょうか。
日本代表の選手たちに、「侍ジャパン」や「なでしこジャパン」などと愛称が付けられますが、馬術は40代という年齢が注目されたためか「初老ジャパン」という愛称が付けられています。「なんだか…」という気もしましたが、中高年の新たな希望の星になるのかもしれません。
開催中のオリンピックにちなんでという事だと思いますが、テレビ番組「題名のない音楽会」ではパリを特集していて、「パリだからこそ生まれた名曲の音楽会」というタイトルが付けられていました。芸術の都とも呼ばれるパリには、昔から芸術家たちが集まってきており、数々の名曲も誕生しています。「なぜ、その名曲がパリで生まれたのか?」を、指揮者の出口大地さんが解説しながら、番組は進行しました。ちなみに、出口さんは、2021年にハチャトゥリアン国際コンクールの指揮部門で日本人初の優勝をされ、日本のオーケストラからのオファーが殺到している注目の指揮者です。
「パリといえば芸術の都と呼ばれていますが、クラシック音楽にとっても重要な街なのですか?」という司会者の問いかけから、番組はスタートしました。
パリだからこそ生まれた名曲、第1曲目は、ロッシーニ作曲のオペラ「ウィリアム・テル序曲」が紹介されました。
オペラ界の巨匠がパリで大ヒットさせた名曲ですが、パリでなければならなかった理由を司会者が聞きますと、出口さんは、「パリ・オペラ座の依頼が無茶ぶりだったからです」と答えていて、「ほほ~っ」と司会者も驚いている様子でした。パリ・オペラ座からの依頼には多くの条件が付けられており、歴史的な興味を引き付ける内容であることや、バレエや大合唱など多彩なスペクタクル要素があることなどが要求されたそうです。当時オペラの上映時間は、3時間程度が相場だった中、この「ウィリアム・テル」はなんと5時間もかかる超大作でした。この様な形態のオペラは、グランドオペラと呼ばれ、当時のパリを象徴する華やかな芸術だったのだそうです。
番組では、出口さんの指揮で「ウィリアム・テル序曲」が演奏されました。テレビ画面のテロップには、「華やかなファンファーレ!パリジャンの好みにドストライクです!」「遠くから行進してくる騎馬隊。特徴的なリズムは馬の足音です!」など、音楽の場面に応じて解説が流れていました。華やかという言葉がぴったりな音楽で、この1曲でその場がとても盛り上がる作品でした。舞台の端で聴いていた司会者も、満面の笑顔で拍手を送っていました。「グランドオペラの序曲というだけあって、華やか!」と感想を話しますと、出口さんも「派手という感じですね」と答えていました。
パリだからこそ生まれた名曲、第2曲目では、ストラヴィンスキー作曲のバレエ「火の鳥」より「魔王カスチェイの凶悪な踊り」が紹介されました。どんどん新しい音楽表現に挑戦していったところが、パリらしさを表しているのだそうです。
当時、世界中から芸術家が集まり、切磋琢磨して新しい文化が作られていきましたが、その中でも特出していたのがロシアの総合芸術プロデューサーのセルゲイ・ディアギレフでした。パリでロシアのバレエ団「バレエ・リュス」を旗揚げし、芸術家たちに音楽や舞台美術、衣装などを依頼して最先端の芸術を取り込んでいました。マティスやピカソなど、有名な芸術家もかかわっていたそうです。そのディアギレフが、駆け出しの作曲家だったストラヴィンスキーに作曲を依頼して生み出された音楽が、この曲です。
出口さんは、新しい音楽表現の具体例として、最初にティンパニの演奏方法を挙げました。ティンパニは、通常、先端をフェルトに包まれたバチで叩いて演奏しますが、木のバチで叩くように楽譜上に指示がされているのだそうです。とても斬新ですね。番組では、フェルトのバチを使用した時の音と、木のバチを使用した時の音を比較していました。フェルトのバチは、音が柔らかく角のない丸い感じの音になり、木のバチは、はっきりとしたインパクトのある音になっていました。出口さん曰く、「木のバチを使用した音は、原始的で野蛮な響きがしますよね」と解説をされていました。
続けて、トロンボーンを挙げました。「火の鳥」の中では、滑らかにスライドさせて音を出すグリッサンド奏法が使われています。当時は、とても珍しい演奏方法で、凶悪な踊りの中で、グロテスクな雰囲気を表現しています。番組で演奏されましたが、「ティンパニの画期的な響きに乗って、魔王と手下の凶悪なテーマが管楽器に現れます」「曲の始まりから、かつてないほど鮮やかで緊張感あふれる音楽!さすが当時の最先端!」というテロップも流れていました。指揮者自らの解説を、演奏を聴きながら見ることができるのはテレビ番組ならではで良いと思いました。演奏後に、「激しかったけれど、凶悪でしたよね~」と司会者と出口さんが感想を話していましたが、とても斬新な音楽という事がよく伝わってきました。
パリだからこそ生まれた名曲、第3曲目では、ガーシュイン作曲の「パリのアメリカ人」が紹介されました。「ラプソディー・イン・ブルー」という作品で有名なガーシュインですが、音楽を学ぶためにパリを訪れた時に、パリの街に魅了されて、この曲を作りました。ガーシュインが、パリで実際に耳にした音をそのまま曲に使っているところが、パリでなければならなかった理由なのだそうです。
当時パリで流行した歌「ラ・ソレーラ」のメロディーがそのまま使用され、パリの街を走っていた車のクラクションのような音も使用したり、パリで作成して特許を取ったサクソフォンも使用しました。そのため、1920年代のアメリカ人から観たパリの街を表現した曲という事なのだそうです。
オーケストラの演奏と同時にテロップでは、「小洒落たパリの街を散歩しているガーシュイン。どこからか「ラ・ソレーラ」の鼻歌が聞こえてきます」「タクシーにクラクションを鳴らされるガーシュイン!」「パリの街のあまりの喧騒に、路地裏に逃げ込んでいきます」「トランペットのソロによる哀愁漂うブルースのメロディー。故郷のアメリカを思い出しています」などの解説が流れ、その光景が本当に見えるかのごとく音楽が作られていることがよくわかり、とても楽しく感じました。
ホールに足を運んで、生演奏ならではの迫力や雰囲気を楽しむことが音楽の醍醐味だと思いますが、テレビ番組では音楽を聴きながら同時に演奏の解説を見ることができたり、演奏者のアップが見れたりと別の楽しみ方もあります。初めて聴く音楽だったり、お子様などは、このような音楽の聴き方の方が、わかりやすくて興味が持ちやすいのかもしれません。
パリのオリンピックも開催中ですし、次回の「題名のない音楽会」でも引き続きパリを特集するそうですので、まだまだパリとの関わりは続くようですね。
最近の投稿
- 大人の生徒さん方の様子
- 指揮者による音楽の違い
- 早春のピアノ教室
- 年明けのピアノ教室
- 2025年メモリアルイヤーの作曲家
- 日本音楽コンクールの話
- 町田樹が語るショパン
- クラシック音楽を支えるプロフェッショナルたち
- 晩秋のピアノ教室
- 3か月でマスターするピアノ
カテゴリー
ブログ内検索
メールマガジン
音楽ナビ
con Vivace について
アーカイブ
- 2025年3月 (2)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (3)
- 2024年11月 (2)
- 2024年10月 (2)
- 2024年9月 (2)
- 2024年8月 (2)
- 2024年7月 (2)
- 2024年6月 (2)
- 2024年5月 (2)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (2)
- 2024年2月 (2)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (2)
- 2023年9月 (2)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (2)
- 2023年5月 (2)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (2)
- 2023年2月 (2)
- 2023年1月 (1)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (3)
- 2022年9月 (2)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (1)
- 2022年6月 (2)
- 2022年5月 (3)
- 2022年4月 (2)
- 2022年3月 (2)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (1)
- 2021年12月 (3)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (2)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (2)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (2)
- 2021年3月 (3)
- 2021年2月 (1)
- 2021年1月 (3)
- 2020年12月 (3)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2020年9月 (2)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (2)
- 2020年6月 (2)
- 2020年5月 (2)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (3)
- 2020年2月 (2)
- 2020年1月 (2)
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (2)
- 2019年10月 (2)
- 2019年9月 (3)
- 2019年8月 (1)
- 2019年7月 (2)
- 2019年6月 (2)
- 2019年5月 (2)
- 2019年4月 (2)
- 2019年3月 (3)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (2)
- 2018年12月 (3)
- 2018年11月 (2)
- 2018年10月 (3)
- 2018年9月 (2)
- 2018年8月 (2)
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (2)
- 2018年5月 (2)
- 2018年4月 (3)
- 2018年3月 (2)
- 2018年2月 (2)
- 2018年1月 (2)
- 2017年12月 (3)
- 2017年11月 (2)
- 2017年10月 (3)
- 2017年9月 (2)
- 2017年8月 (2)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (2)
- 2017年5月 (3)
- 2017年4月 (2)
- 2017年3月 (2)
- 2017年2月 (2)
- 2017年1月 (2)
- 2016年12月 (3)
- 2016年11月 (2)
- 2016年10月 (2)
- 2016年9月 (1)
- 2016年8月 (2)
- 2016年7月 (3)
- 2016年6月 (2)
- 2016年5月 (2)
- 2016年4月 (2)
- 2016年3月 (2)
- 2016年2月 (2)
- 2016年1月 (5)
- 2015年12月 (2)
- 2015年11月 (1)
- 2015年10月 (3)
- 2015年9月 (2)
- 2015年8月 (2)
- 2015年7月 (2)
- 2015年6月 (3)
- 2015年5月 (3)
- 2015年4月 (2)
- 2015年3月 (2)
- 2015年2月 (2)
- 2015年1月 (5)
- 2014年12月 (3)
- 2014年11月 (2)
- 2014年10月 (3)
- 2014年9月 (3)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (4)
- 2014年6月 (2)
- 2014年5月 (3)
- 2014年4月 (3)
- 2014年3月 (4)
- 2014年2月 (2)
- 2014年1月 (4)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (2)
- 2013年10月 (5)
- 2013年9月 (3)
- 2013年8月 (2)
- 2013年7月 (2)
- 2013年6月 (2)
- 2013年5月 (3)
- 2013年4月 (4)
- 2013年3月 (3)
- 2013年2月 (2)
- 2013年1月 (4)
- 2012年12月 (3)
- 2012年11月 (4)
- 2012年10月 (1)
- 2012年9月 (2)
- 2012年8月 (3)
- 2012年7月 (4)
- 2012年6月 (5)
- 2012年5月 (4)
- 2012年4月 (4)
- 2012年3月 (5)
- 2012年2月 (4)
- 2012年1月 (6)
- 2011年12月 (5)
- 2011年11月 (3)
- 2011年10月 (3)
- 2011年9月 (2)
- 2011年8月 (2)
- 2011年7月 (4)
- 2011年6月 (2)
- 2011年5月 (3)
- 2011年4月 (2)
- 2011年3月 (3)
- 2011年2月 (3)
- 2011年1月 (4)
- 2010年12月 (4)
- 2010年11月 (2)
- 2010年10月 (4)
- 2010年9月 (1)
- 2010年8月 (4)
- 2010年7月 (3)
- 2010年6月 (54)
