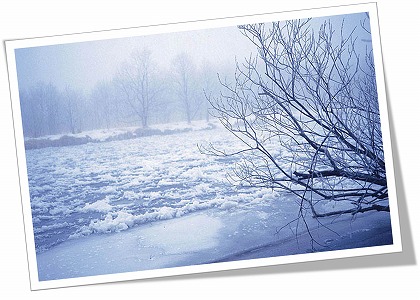
(この記事は、2025年1月27日に配信しました第414号のメールマガジンに掲載されたものです)
今回は、年明けのピアノ教室の様子です。
2025年がスタートして、もうすぐ1カ月が経とうとしています。年末年始は、特に出かけることもなく、自宅でゆっくりと過ごされた生徒さんもいますし、息子・娘さん家族が集まり、賑やかというよりも毎日バタバタと忙しく動き回っていた生徒さんもいらっしゃったようです。
ある生徒さんは、毎年娘さん家族とクリスマス会を開いていたそうですが、お孫さんがインフルエンザにかかってしまったため延期となり、年末に開催したそうです。「大晦日に、みんなで集まったのよ。時期としては、なんだかねえという感じなんですけれど。でも、孫たちも大きくなってきたので、だんだんと予定も合わなくなると思うのでね」とお話されていました。お孫さんの成長は、嬉しい反面、段々と関わり合いが少なくなってしまうという寂しさも感じているのかもしれません。
また別の生徒さんは、受験を控えているお孫さんがいるそうで、娘さんが付きっ切りでフォローをするために、そのお孫さんの一番下の兄弟のお世話をされていたとお話されていました。お世話していたお孫さんは、体調を崩しやすいようで、なかなか大変だったそうです。
「一番上の孫は、娘の言う事をハイハイ言って素直に言われたようにできるから、計画通りに進められて良かったみたいなんだけど、今度受験する2番目の孫は、女の子だから、娘の言う事を全然聞かなくて反発ばかりしているから、結構大変みたいなのよ。だから、上の子が入った学校とかのレベルには全然届かなくて」などとお話をされていて、結構心配されている様子が伺えました。普段から、フルタイムでお仕事をされている娘さんのお手伝いをされていて、お孫さんとの関わりも多い分、より心配になってしまうのかもしれません。
お子様の生徒さんは、クリスマスにお正月とイベント続きで、楽しく過ごされたようです。「今日、ピアノが終わったら、お父さんがケンタッキーのパーティバーレルを予約してくれるんだ」と嬉しそうにお話をされた生徒さんは、クリスマスが終わると「明日からスキーに行くんだ」と、これまた嬉しそうにお話をされていました。
「スポーツ万能の〇〇ちゃんだから、ご家族の中で一番スキーも上手なのかしら?」と聞いてみますと、「ううん、パパが一番上手。スキーに行くときは、いつも5時に起きて行くから早いんだよね~」と話をしていました。「そうね。ちょっと朝早いけれど、でも移動中は車の中でずっと寝ているんでしょ?その間、ずっとお父様が運転されていて、着いたらスキーをされるんだから大変そうよね。お父様もお疲れだろうから、いたわってあげてね」とお話をしますと、「うんっ」と元気よく返事をされていました。
小学生姉妹の生徒さんは、昨年秋から始まったピアノ・コンクールのファイナルが相次いであり、大忙しの年末年始でした。以前から、小学校の行事でのピアノ伴奏やピアノ教室内のオーディション、コンクールなどに積極的に参加してきました。今回は、初めて参加するコンクールと、昨年度受けたコンクールのリベンジで、2つのコンクール参加のために、昨年春頃から準備をしてきました。ピアノコンクールも様々ありますので、コンクール選びから選曲まで、練習を始める前段階から、生徒さんのお母様と頻繁に連絡をとって相談してきました。
非常にレベルの高いコンクールでは、予選を通ったら万々歳という考え方もありますが、「そんなに凄いコンクールでなくていいですし、小さいコンクールでいいので、こんなに頑張ったから良い結果がもらえたねという体験をさせたいんです」という旨の話をされていました。ご自宅にグランドピアノがある方や、音大の教授クラスの先生に日頃から習っている方も、コンクールには大勢参加されるので、コンクールのレベルの見極めや参加する部門選び、生徒さんの強みを活かした選曲など、慎重に下調べをしました。
選曲についても、私の方から指定するのではなく、いくつか曲をご紹介して音源を聴いていただき、生徒さんに選んでいただきましたので発表会と同じ流れになりました。生徒さんのお母様は、ピアノの経験がありますのでいろいろとよくご存じですが、「こんなにきれいな曲があるのですね。知らなかったです!」と感激されていて少しビックリしました。
姉妹の生徒さん共に、それぞれコンクールで弾きたい曲が見つかり、まずはよかったと思っていました。妹さんは、2つのコンクールで同じ曲を使えるので、ずっと練習をしつつ、普段使っている練習曲の教材を進めたり、表現力を強化するために少し他の曲を取り入れたりして、コンクールの準備をしてきました。一方で、お姉さんは、妹さんと同じ2つのコンクールを受けるのですが、同じ曲が使えなかったために、2つの曲を並行して練習することになりました。曲のタイプも、異なる曲想のものでしたので、練習は大変だったかと思います。
昨年度受けたコンクールのリベンジが、先の開催だったのですが、賞をいただくことができず、生徒さんやご家族のみなさんもかなりがっかりされたそうで、お母様からも、大変残念な様子のご連絡をいただきました。私も、「結果を出させてあげられず、申し訳ないです」と返信をしましたが、その後も大変気がかりで、かなり心配をしましたが、「子供たちは、次のコンクールを頑張ると、もう気持ちを切り替えています」とご連絡をいただきました。
レッスンの時に、そのコンクールでの感想を聞きますと、開口一番「黒鍵が細かった」と揃ってお話をされていてびっくりしました。「以前、オーディションの本番で弾いたピアノと同じ型番なんだけど…もう覚えていないよね?」と聞きますと、「えっ?そうなの?全然覚えてない」との事で、ピアノに慣れていなかった事も、残念な結果に少し影響しているのかと思い、早速対策を取りました。
今回初めて参加するコンクールのファイナルで使用するピアノの型番を調べ、そのピアノで練習できる場所をご紹介したところ、「早速、年明けに練習してきます」と、すぐに予約をしていただいたようでした。そして、練習の際には、ピアノの蓋を全開にして、譜面台も取った状態にして、なるべく本番に近い状態で練習することもお伝えしました。その時の音源もメールに添付していただき、良いところはこの調子で、惜しいところは細かくアドバイスをしました。
春から準備をしてきて、予選、本選を通過して、いよいよ最後の本番なので、ご家族の許可をいただき、生徒さんには内緒で聴きに行きました。生徒さんの出番が近づくと、私の緊張もピークに達し、自分がコンクールや本番に出るときの緊張感とはまた異なる緊張感で、舞台を見つめました。お二人とも、緊張はしているのかもしれませんが、普段と同じような様子で舞台に登場し、落ち着いて演奏もしていて、頼もしいなあと思うと同時に、「これまでの頑張りが、結果に結びつきますように」という祈りの気持ちも込みあげてきました。
姉妹お二人の部門全ての演奏が終わったところで、会いに行きますと、お姉さんは「あ~っ、先生!」という感じで笑顔になり、妹さんの方は、とてもビックリしたようで言葉も出ないという様子でした。お母様が、「先生から紹介されたところで練習できて、子供達も安心してピアノを弾けたようです」とお話をされていて、よかったなと思ったのですが、やはりお二人とも、「今回のピアノの黒鍵は、やっぱり細かった」と同じ感想を話していました。
「あら~、練習に行ってくれたところのピアノと同じ型番のピアノなんだけどね。あとは照明の問題かもしれないわね。スポットライトの強さとか、照明の角度によって見え方が変わるかもしれないわね。あとは、ご自宅にその型番のピアノをご用意していただくとか…。3メートル近い長さがあるので、結構大きいですから、場合によってピアノが部屋からはみ出るか、ピアノを弾くご自分がはみ出るか…」とお話をしますと、生徒さんやご家族が声を上げて笑っていました。
結果発表の時にはご家族水入らずでと思い、結果発表前に会場を後にしましたが、その後お母様から連絡があり、姉妹揃って賞をいただけたと嬉しいご報告がありました。私自身は、昨年度の残念な結果から、ずっと大きな宿題を抱えたままという気持ちで過ごしてきましたので、ようやく結果が出せたという気持ちですし、なによりも、姉妹揃っての受賞という事に心から安堵しました。
ようやく長かったコンクール参加が終わった訳ですが、早くも「今年度もコンクールに出たい」という、またまた積極的なお話がありましたので、次に向けて準備が始まりそうです。

(この記事は、2024年11月11日に配信しました第409号のメールマガジンに掲載されたものです)
今回は、晩秋のピアノ教室の様子です。
11月に入り、急に肌寒くなってきました。生徒さん方も、「今日は寒いですね~」とおっしゃりながらレッスン室に入って来られます。
「寒くなってきましたから、手を冷やさない対策をとって、お教室にいらして下さいね。近所だから大丈夫と思っても、直ぐに手は冷えてしまうこともありますし、手が温まって調子が出てきた頃にはレッスン時間が終わり、ではまた来週となったら、ちょっとがっかりしちゃいますしね」とお話しますと、そうそうと頷いたり、ちょっと笑っている方もいらっしゃいます。私自身は、既に手袋を携帯していて、防寒対策はバッチリです。
発表会も終わり、年内のイベントはこれにて終了というのが毎年の流れですが、今年はまだまだ本番を控えている生徒さん方がいらっしゃいます。
小学生の生徒さんは、この時期にどの学校でも生活発表会や音楽会での合奏が定番です。
合奏の譜読みは問題なくても、リズムにやや不安があるという生徒さんは、レッスンで細かくリズムの確認を行っています。合奏の場合、休符が続いて自分が演奏しない時間があることも珍しくなく、4小節休みとか、8小節休みという事もあります。ピアノでは、まずそのようなことはないので、気を付けなければいけないポイントです。
今回、生徒さんが練習している曲にも、同じように数小節休みという箇所がありました。きちんと拍を数えていないと、他の方とズレてしまいかねないので、自分が演奏していなくても、常に拍を意識しておくようにアドバイスをしました。そして、「できたら学校の先生に、主にメロディーを担当している楽器の楽譜を1部下さいと、お話してみてくれるかな?〇〇ちゃんが数小節休符の時に、他の楽器がどのような音楽を演奏しているのかわかっている方が、休符が終わってまた演奏を始めるときのタイミングも取りやすいし、音楽の全体の流れもわかる方がいいと思うのよね」とお話しますと、「わかりました。先生に話してみます」と返事をしてくれました。
個人レッスンだからこその利点を生かして、生徒さんがいろいろな場面で、音楽を通して活躍できるお手伝いができることは嬉しい限りです。
小学生姉妹の生徒さんは、2つのコンクールにチャレンジしていて、春から大忙しの日々を過ごしています。昨年は、惜しくも残念な結果となり、生徒さんもご家族もかなりがっかりしてしまったようですし、私も結果を出させてあげられず申し訳ない思いをしました。今年は、より生徒さんに合ったコンクールを吟味し、曲についても昨年よりも生徒さんの特性がよりアピールできる曲目を選んでご紹介しました。
コンクールとはいえ、「先生にこれを弾けと言われたから、別に好きな曲ではないけれど弾いている」というようでは、たとえ良い結果が得られたとしても、心底喜べるのか疑問に思うので、何曲かピックアップして、最終的に生徒さんに選んでもらいました。生徒さんのお母様に、曲目や音源をお伝えしたのですが、早速ご家族で音源を聴いて、一番気に入った曲を弾くことになりました。
予選の当日は、さすがに私もそわそわと落ち着かず、結果が出る頃には緊張もピークに達し、困った時の神頼みではないですが、「予選だけはなんとか突破を…」「姉妹そろって予選通過を…」と願わずにはいられませんでした。終わってみれば、危なげなく予選を突破でき、生徒さんもご家族も大変喜んでいました。
次は本選ということで、生徒さんのお母様も、「いよいよ、ここからが本番で、ここまで来たからにはファイナルに進みたい」と、いつも熱心なお母様も更に熱が入っているようで、普段はレッスンに同席されないのですが、「レッスンを見学してもいいですか?」と言われ、同席されていました。レッスン中も瞬き一つしないくらい食い入るような姿勢で見学され、これまで一番の課題だった箇所の演奏がとても上手に出来て私が褒めた時には、お母様が思わず、「今の!今の演奏よ!」と声をかけていました。
生徒さん自身も、手ごたえを掴めたようですし、私だけでなく、普段から一番傍で見守ってくれているご家族から褒められたことが嬉しかったようで、盛んに照れている表情をしていました。
もうすぐ本番という時に私が高熱を出してしまい、レッスンが急遽休講となってしまった時にも、「できる限り」と思い、お母様に連絡を取り、自宅での演奏を録音して送って頂くお願いをしました。そして、その録音を聴いて、良かったところ、改善点、練習方法などを楽譜に書き込んでメールに添付し、練習の参考にしていただきました。数日後にも、再び同じことを繰り返し、いよいよ本選の当日になりました。
本選の直前に、私が体調を崩してご迷惑をかけてしまい、そのために本選で結果が出なかったらと思うと、予選とはまた違った緊張感を持ちましたが、こちらも、めでたく突破することができました。
お母様から結果のご連絡をいただきましたが、冒頭に「やりました!」と書かれていて、いかに喜んでいらっしゃるのかがよく伝わってきました。私も嬉しさと安堵の気持ちで一杯でした。
次は、本当に最後のファイナルですが、その前になんと昨年残念な結果となったコンクールの再チャレンジがあります。元々は、より生徒さんに合ったコンクールをという事で、他のコンクールにチャレンジし始めたわけですが、その途中で「昨年参加したコンクールも、また受けてみたい」というご相談を受けていました。私はちょっと驚きましたが、生徒さんのやりたいという気持ちを尊重したいので、快諾して再チャレンジも始めたのです。
このコンクールも予選を無事に通過することができ、次に向けて生徒さんも頑張っている最中です。レッスンでは、細かい所にこだわって、ひたすら上手にできるまで何回も反復練習をしたり、たった1回の本番で全てを出し切れるように精度を上げる練習など、とても楽しいとは思えないような練習もしなければならない場面も出てきます。曲にも飽きてくるでしょうし、気が乗らないとか、練習しているのにちっとも上手くなった気がしないという事もあるかもしれません。なかなか大人でも気が滅入ることを、小学生が自らチャレンジしているのですから、本当に凄いなと思います。
最後の本番で、これまでの集大成が披露できるように、引き続き私も毎回のレッスンを大切に進めていきます。

(この記事は、2024年9月2日に配信しました第404号のメールマガジンに掲載されたものです)
今回は、晩夏のピアノ教室の様子です。
大型の台風が発生して、思った以上に進路予想が目まぐるしく変わり、また速度もかなり遅く、日々どこに向かうのか今後どうなるのか心配しながら天気予報を見ていた方も多かったのではないでしょうか。レッスンにいらしている生徒さん方とも、そのようなお話をしていたところですが、温帯低気圧に変わり、ちょっとほっとしているところです。
台風が接近している時にレッスンが予定されている場合、生徒さん方の安全を考えて終日または半日の休講にします。台風だけではなく、大きな地震や大雪などの天災全般に共通するものです。生徒さんの中には、「徒歩なので行けます!」と言われる方もおり、そのくらいピアノのレッスンに前向きという事で大変嬉しく思いますが、レッスン中に天気が大荒れになってしまい帰宅できないとか、帰宅途中で何かあっては大変です。そのため「急な休講の場合は、後日補講をしますので、どうぞご心配なさらずに。日時を改めてレッスンしましょう」とお話をしています。
今回の台風でも、レッスンに重なりそうな方が多く、予定通りにレッスンが行えるのか心配していましたが、どうにか休講せずにレッスンを行うことができました。しかし、時間帯によっては、土砂降りの中来られた生徒さんもいて、「本当にすごい雨で…」と話し始め、「ここまで来るのに本当に大変でした」と話が続くのかと思っていたら、「長靴を履いてきてしまったから、私、ちゃんとピアノのペダルが踏めるのかしら?」と、意外な話の展開になり驚きました。
最近、趣味のスポーツをしている最中に足を痛めてしまったそうで、救急車で病院に運ばれてしまうという出来事があり、ピアノのレッスンをお休みされていました。ピアノ教室も夏休みがあり、お休みが続いていましたので、「やっと今日はピアノのレッスンに行ける!と楽しみにしていたんです」ともお話をされました。「長靴ですと、確かに足が動かしにくいですが、このお天気ですと仕方がないですしね。無理なくペダルを使ってみてください」とお伝えしてレッスンをしました。
そして、レッスンが終わるところで、「前に、先生の演奏を録音させていただいたでしょ?あれを何回も聴いているんですけれど、どうも私の弾いている曲と同じように聴こえなくて、全然違う曲に聴こえるんです。こうやって、よ~く何回も聴いているんですけれど…」とお話をされました。「なるほど、同じ楽譜を見て同じピアノで弾いているので、同じ曲なんですがね」とニコっとしながらお返事をしますと、「そうですよね~」と笑っていました。
「まあ、いろいろと理由があるとは思いますが、例えばこの箇所を普通に弾きますと・・・・。(演奏後に)こうですよね。〇〇さんもそのように弾いていらっしゃいますが、それを、私が録音した時には、メロディーはこの箇所なので、そこを少し強く目立つように、(メロディーだけを弾いて)このように弾いていて、他の箇所は伴奏なので、(演奏しながら)このように少し弱く弾いていたんです。それを合体して弾くと…(演奏後に)こうなるわけです」と演奏を交えながら解説をしました。
生徒さんは食い入るように熱心に聴いていて、「あ~」とか「そうそう」とか、いろいろな反応をされていました。「楽譜には、この音はメロディーだからちょっと強めに弾くとか、これはそこまで重要な音ではないので、弱めにとか一切指示が書かれていないので、演奏する方がいろいろと見抜かないといけないんですよね。いろいろな音をよく整理して弾くと、演奏がすっきりとまとまりますし、またこのピアノという楽器は、一度にいろいろな強さで音が出せます。ピアノの誕生以前の楽器では、できなかったので画期的な楽器と言えるかもしれませんね」とも説明をしました。
生徒さんは、「なるほど~」と何回もうなずきながらおっしゃっていました。「なので、またご自宅などで録音を聴くときに、そのような個々の音の強さを変えながら弾いているという視点で聴いてみると、またちょっと聴こえ方が違ってくるかもしれませんね」とお話をしますと、「そうですね。早速自宅でまた聴いてみます」とおっしゃっていました。
ピアニストなどのプロの演奏は、すごいとか上手という事はどなたもお分かりになるのですが、では何がすごいのか、どのような工夫をしているのか、どの部分が自分の演奏と異なるのかというところは、わからないこともあります。レッスンで、具体的に演奏をしながら細かく説明をすることで、生徒さん方に理解していただけたり、納得していただけたり、ご自分の演奏にも取り入れてみようと思っていただけたり、また鑑賞するときの楽しみ方の広がりを感じていただけたら嬉しい限りですし、生徒さん方も、ピアノのレッスンに来てよかったと思って下さるのかなあとも思っています。
この生徒さんが、演奏や音楽の鑑賞の仕方が、どのように変化するのか楽しみです。
お子様の生徒さん方は、夏休みをそれぞれ楽しまれているようで、ちょっとうらやましいなあと思ってしまいます。使用している楽譜の最後の曲に取り掛かっている生徒さんは、「今日ね、ピアノが終わったら楽しみなことがあるの」と話していました。「え~、何、なに?」と聞きますと、「今日は、夜更かしして韓流ドラマを見るの!」とニコニコしながら話していて、夜更かしが楽しみというのも、かわいらしいなあと思って聞いていました。
また、別の生徒さんは、もうすぐ学校が始まるねと話しますと、「え~、やだ~。ずっと夏休みがいい」と、これもまたよくある小学生の感想で、こちらもまた気持ちがわかるなあと思いながら聞いていました。
既に、一足早く2学期が始まっている生徒さんは、「今日は始業式の日なのに、授業もあるし給食もあって疲れた」と既にお疲れモードだったり、その他にも、「夏休みは、いろいろな習い事の大会とか合宿とかがあって、すっごい忙しい」と話している生徒さんもいて、「学校が始まった方が、かえって楽かもしれないわね」と話しますと、「ああ、そうかもっ!」と妙に納得していて、むしろ私の方が驚くという事もありました。
大人の生徒さんの中には、1000人以上の収容客席を持つ大ホールで、スタインウェイとベーゼンドルファーのピアノの弾き比べができるという企画に参加された方がいます。難曲や大曲も「譜読みは難しいけれど、楽しいです」とおしゃり、弾きこなす生徒さんなのですが、発表会の参加をお勧めしますと、「小さい頃に発表会とかは出たので、もう人前で弾くのはいいです」と、ご丁寧な口調で毎回お断りされてしまうのです。レッスン室のピアノもグランドピアノとしては小さめですし、レッスン室も狭いですから音の響きもあまりない環境でしか弾いていないので、日頃からもったいないなあと思っていました。
偶然にも、先程の弾き比べの企画を知り、早速この生徒さんにお知らせしたところ、参加されることになりました。非公開のため、後日お話を聞きますと、「今弾いているラフマニノフは、スタインウェイで弾いた方がとても合うなあという感じで、ベートーヴェンの月光は、ベーゼンドルファーで弾いた方が落ち着いた感じが合っていて…、そうそう坂本龍一の曲は、スタインウェイの方がよかったです!」と、饒舌に話をされていました。
「同じ曲を、2台のピアノで弾き比べをして、こんなにもピアノによって違うんだと思って、とっても面白かったです!」と、相当楽しかった様子が伝わってきて、私もとても嬉しくなりました。「そうなんですよね。ご自分で、同じ曲を、一度に異なるメーカーのピアノで、今回のように楽器のサイズも近いもので弾き比べると、一番違いがわかるんですよね。以前にも、ピアノの弾き比べ体験はされていますが、今回は大ホールでの弾き比べですから、音もよく響きますし、なかなか贅沢な企画でよかったですね」とお返事をしました。
生徒さん方の充実ぶりを見ると、私も大いに刺激を受け、頑張ろうというエネルギーもいただいている気がします。今年も残り4カ月ですので、大いに張り切ってレッスンを進めていこうと思います。
最近の投稿
- オーケストラの日
- 他の先生から引き継いだ生徒さん
- 大人の生徒さん方の様子
- 指揮者による音楽の違い
- 早春のピアノ教室
- 年明けのピアノ教室
- 2025年メモリアルイヤーの作曲家
- 日本音楽コンクールの話
- 町田樹が語るショパン
- クラシック音楽を支えるプロフェッショナルたち
カテゴリー
ブログ内検索
メールマガジン
音楽ナビ
con Vivace について
アーカイブ
- 2025年4月 (2)
- 2025年3月 (2)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (3)
- 2024年11月 (2)
- 2024年10月 (2)
- 2024年9月 (2)
- 2024年8月 (2)
- 2024年7月 (2)
- 2024年6月 (2)
- 2024年5月 (2)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (2)
- 2024年2月 (2)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (2)
- 2023年9月 (2)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (2)
- 2023年5月 (2)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (2)
- 2023年2月 (2)
- 2023年1月 (1)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (3)
- 2022年9月 (2)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (1)
- 2022年6月 (2)
- 2022年5月 (3)
- 2022年4月 (2)
- 2022年3月 (2)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (1)
- 2021年12月 (3)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (2)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (2)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (2)
- 2021年3月 (3)
- 2021年2月 (1)
- 2021年1月 (3)
- 2020年12月 (3)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2020年9月 (2)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (2)
- 2020年6月 (2)
- 2020年5月 (2)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (3)
- 2020年2月 (2)
- 2020年1月 (2)
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (2)
- 2019年10月 (2)
- 2019年9月 (3)
- 2019年8月 (1)
- 2019年7月 (2)
- 2019年6月 (2)
- 2019年5月 (2)
- 2019年4月 (2)
- 2019年3月 (3)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (2)
- 2018年12月 (3)
- 2018年11月 (2)
- 2018年10月 (3)
- 2018年9月 (2)
- 2018年8月 (2)
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (2)
- 2018年5月 (2)
- 2018年4月 (3)
- 2018年3月 (2)
- 2018年2月 (2)
- 2018年1月 (2)
- 2017年12月 (3)
- 2017年11月 (2)
- 2017年10月 (3)
- 2017年9月 (2)
- 2017年8月 (2)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (2)
- 2017年5月 (3)
- 2017年4月 (2)
- 2017年3月 (2)
- 2017年2月 (2)
- 2017年1月 (2)
- 2016年12月 (3)
- 2016年11月 (2)
- 2016年10月 (2)
- 2016年9月 (1)
- 2016年8月 (2)
- 2016年7月 (3)
- 2016年6月 (2)
- 2016年5月 (2)
- 2016年4月 (2)
- 2016年3月 (2)
- 2016年2月 (2)
- 2016年1月 (5)
- 2015年12月 (2)
- 2015年11月 (1)
- 2015年10月 (3)
- 2015年9月 (2)
- 2015年8月 (2)
- 2015年7月 (2)
- 2015年6月 (3)
- 2015年5月 (3)
- 2015年4月 (2)
- 2015年3月 (2)
- 2015年2月 (2)
- 2015年1月 (5)
- 2014年12月 (3)
- 2014年11月 (2)
- 2014年10月 (3)
- 2014年9月 (3)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (4)
- 2014年6月 (2)
- 2014年5月 (3)
- 2014年4月 (3)
- 2014年3月 (4)
- 2014年2月 (2)
- 2014年1月 (4)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (2)
- 2013年10月 (5)
- 2013年9月 (3)
- 2013年8月 (2)
- 2013年7月 (2)
- 2013年6月 (2)
- 2013年5月 (3)
- 2013年4月 (4)
- 2013年3月 (3)
- 2013年2月 (2)
- 2013年1月 (4)
- 2012年12月 (3)
- 2012年11月 (4)
- 2012年10月 (1)
- 2012年9月 (2)
- 2012年8月 (3)
- 2012年7月 (4)
- 2012年6月 (5)
- 2012年5月 (4)
- 2012年4月 (4)
- 2012年3月 (5)
- 2012年2月 (4)
- 2012年1月 (6)
- 2011年12月 (5)
- 2011年11月 (3)
- 2011年10月 (3)
- 2011年9月 (2)
- 2011年8月 (2)
- 2011年7月 (4)
- 2011年6月 (2)
- 2011年5月 (3)
- 2011年4月 (2)
- 2011年3月 (3)
- 2011年2月 (3)
- 2011年1月 (4)
- 2010年12月 (4)
- 2010年11月 (2)
- 2010年10月 (4)
- 2010年9月 (1)
- 2010年8月 (4)
- 2010年7月 (3)
- 2010年6月 (54)
