
(この記事は、2024年4月1日に配信しました第394号のメールマガジンに掲載されたものです)
今回は、春を迎えたピアノ教室の様子です。
今年の春は、急に寒くなったり夏日さながらの陽気になったりと、気温の変化が激しい気がします。そのためなのか、生徒さんの中には体調を崩してしまった方が何人もいて、心配をしているところです。
お子様の生徒さんは、3学期が終了して春休み真っ最中です。新学期になるとクラス替えがありますので、今のクラスが名残惜しいのかと思いきや、「いや、別に…」と答える生徒さんが多くて、意外に人間関係がさっぱりしているのだなあと思ったりします。新しい出会いの期待の方が大きいのかもしれませんね。
楽しく春休みを過ごしてほしいと思いつつ、ピアノ教室では、3月は発表会の曲決めと練習を始める時期になりますので、そうのんびりとはしていられません。生徒さんご本人に、今年の発表会でどんな曲を弾きたいのかを考えてもらい、生徒さんのご家族の希望と、生徒さんの長所を生かすような曲想やテクニックを踏まえた曲をいくつかご紹介して、音源を聴いていただき、最終的に決めてもらいます。決まらなかった場合は、また新しく数曲を選んでご紹介して、音源を聴いてもらうという事を繰り返す事になります。
生徒さんの中には、発表会の曲選びがご家族の楽しみの一つになっている方もいます。「そろそろ、発表会の曲を決める季節になりましたね。幾つか曲を選んできましたので、ご自宅でYouTubeなどを利用して聴いてみてくださいね。ちなみに、この最初の曲は、〇〇ちゃんがすごく気に入りそうなので聴いてみてくださいね。それで、次回のレッスンで、どの曲が弾きたいのか教えてくださいね」とお話しますと、お母様が「あら~、楽しみね。早速聴いてみましょうね」と生徒さんに話しかけていて、生徒さんがニコニコしながら「うんっ!」と返事をしていました。発表会本番前から、楽しみを共有されている様子が伺えて、素敵だなあと思いました。
翌週のレッスンでは、早速「この前、先生が言っていた最初の曲、すっごく好き。それから一緒に組み合わせて弾くって言っていた曲の方も好き。これにする」と、お返事を頂きました。だいぶ張り切って練習をしていますし、レッスンでは、紛らわしい箇所について曲の作りを一緒に見て、どうやって区別をしていくのか、特にどこを気を付ければ弾けるのかをお話して、一緒に部分練習をしました。曲全体の中で一番難関な箇所を自力で弾けるようになりましたので、1曲目の譜読みもほぼ出来た状態まで進みました。これから2曲目の譜読みも始まりますが、このまま楽しく進めてほしいものです。
別の小学生の生徒さんは、「この曲が弾きたいのですが、いかがでしょう?」とお母様からご連絡を頂きました。どうも、以前どこかでその曲を弾いていた人がいて、弾きたいと思ったそうなのです。私が当初想定していた難易度よりも易しい曲でしたので、譜読みも早く進み、「だいぶ早く曲が仕上がりそうなので、これならもう1曲組み合わせると良さそうですね」と、お母様に話したところ、その場にいた生徒さん本人が「もう1曲弾くのはいや。これだけがいい」とお返事をされていました。お母様も私と同意見でしたので、後日追加をする1曲を選んで、ご紹介することになりました。
その後、どんなお返事になるのかと思っていたのですが、なんと「コンクールを受けてみたいんです」というお話が出てきました。以前からそのような話をされていて、コンクールのご紹介もしたのですが、それから少し経っていましたので、どうされるのかと思っていました。しかも、姉妹揃ってチャレンジしたいとのことでした。その後も、お母様と頻繁に連絡を取って、既に練習をしている発表会の曲、追加の新しい曲、コンクールの曲、普段のテクニックの曲と4曲練習するのは大変なので、コンクールで弾く曲を発表会でも追加の曲として弾くという事になりました。発表会で、コンクールのリハーサルのような事もできるので、場慣れもできそうです。また、ピアノ教室内のオーディションや、他のシーズンに行われる別のコンクールにも挑戦したいとのことで、ピアノに対して大変意欲的で熱心な姿勢にとても驚きました。かなり責任重大になりますが、生徒さんの力を引き上げて、努力が良い結果に結びつくように、気を引き締めてレッスンを行いたいと思っています。
新学年を迎えて新しい学校やクラスに進まれるお子様とは異なり、大人の場合は、明確な区切りが無いのですが、それでも春は何か新しいことを始めようかと思わせる季節のようです。先日も、相次いで大人の方の体験レッスンを行いました。
お一人は、結構なブランクがあるとはいえ、ピアノ歴20年というベテランの方です。20年間もピアノを弾いていた経験がありますから、「以前弾いていた曲は、どんな曲ですか?」とお聞きしますと、ベートーヴェンのソナタやショパンのワルツなど、なかなかの難易度の曲名が挙がりました。ずっとクラシックを弾いてきたので、せっかくまたピアノを弾くなら、今度はポピュラーな曲を弾きたいそうです。「ずっと弾いていない時期があったので、全然弾けなくなっちゃって…」とおっしゃっていましたので、用意しておいた曲のうち、比較的易しいレベルの曲の楽譜を広げて、「このくらいの曲は、弾けそうですか?」とお聞きしました。少し楽譜を見てから、「片手なら弾けそうです」との事なので、弾いていただいたところ、ほぼノーミスで弾けていました。「初見なのに、ほとんど弾けています。凄いですね。左手はいかがでしょう?」とお話をして、今度は左手を弾いていただきました。ヘ音記号で書かれた楽譜を読む事や、左手の指を動かすことに少し苦労される方も珍しくない中、この方はすらすらと弾いていて、またまたびっくりしました。「左手もいいですね。片手ずつは弾けていますから、次はもう両手を合わせて弾くしかないですね」とお話をしますと、ニコッとされながら、かなり順調に弾いていました。
同時に弾く音だけど長さが異なる箇所に、少々ややこしさを感じているようで、少し部分練習をしましたが、あっという間に弾きこなし、気が付けば体験レッスンで3曲ほど弾けるようになっていました。葉加瀬太郎さんの曲が弾きたくて、楽譜も用意して練習をしているそうですが、途中でよくわからないところがあって、その先が進めないとのお話もされていました。レッスンでは、あらかじめ決められたカリキュラムはないので、弾きたい曲だけを1曲レッスンしたり、テクニックの教材と好きな曲という組み合わせ、弾きたい曲を複数レッスンすることも、クラシックとポピュラーの曲を交互に弾くなど、いろいろと自由にレッスンができる事をお話しました。楽譜をお持ちいただければ、よくわからないところのレッスンも可能という事もお話したところ、「あっ、いいですね」とお返事をされていました。1人で弾いていますと、どうしてもよくわからない指使いやリズムなどが出てくる事も多々あり、行き詰ってしまう事もあると思います。レッスンで解消して弾けるようになったら、ピアノを弾く楽しみもまた広がっていくと思いますので、今後も楽しみです。
ちょうど同じタイミングで、他の大人の方も体験レッスンにお見えになりました。レッスンのご要望として、シャンソンが弾きたいと記入されており、ちょっと珍しいと思いました。シャンソンというと一般的には歌なので、シャンソンを歌いたいから声楽科の体験レッスンを受けてみたいという事になると思うのですが、シャンソンをピアノで弾きたいという事は、どういうことなのかと少し不思議に思っていました。体験レッスン当日、ご本人にお話を伺ったところ、既に他の教室でシャンソンのレッスンを受けていたとのことです。しかし、コロナの影響でレッスンが休止となり、やっとレッスンが再開されたところに、先生の体調不良でレッスンが無くなってしまったのだそうです。そこでピアノを習って、弾き歌いなんかもできたらいいなあと思って、体験レッスンを申し込んだとのことでした。ピアノは、少し弾いたことがあるとのことでしたので、易しくアレンジされたシャンソンの名曲をいくつか用意して、様子を見ながら曲を選び体験レッスンを行いました。同じ曲でも難易度が異なる楽譜を用意したので、実際に見ていただき、弾けそうなアレンジの楽譜を見て、メロディーを少し弾いていただきました。選んだ曲がお好みとぴったり合ったようで、「こういう曲が弾きたかったの!」と大喜びで、即入会され、楽譜もその場で注文し、次回のレッスンのお約束もしました。大変良いスタートが切れたようなので、これから進み具合を見ながら、まずは体験レッスンで扱った曲を仕上げていこうかと思っています。
今後、幼稚園生のお子様の体験レッスンも予定されていますので、出会いの春はまだまだ続きそうです。
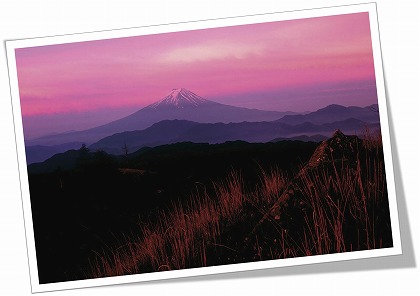
(この記事は、2024年1月22日に配信しました第389号のメールマガジンに掲載されたものです)
今回は、新年を迎えたピアノ教室の様子です。
能登半島の地震に羽田空港の事故など、波乱の年明けになってしまった2024年ですが、ピアノのレッスンは予定通りに進められています。年明けのレッスンでは、「あけましておめでとうございます…と言っていいものか、他になんと言ったらよいのか悶々と考えつつ、結論が出ないままこうしてお話しています」と訳の分からない挨拶をしていました。
生徒さん方も、「そうですよね。本当にびっくりしました」と驚きを隠せない様子の方が大変多く、「ご親戚やお知り合いの方々は、大丈夫ですか?」と尋ねましたが、生徒さん方の中には、被害に遭われた方はいらっしゃいませんでした。ただ、「数年前に、金沢や能登など、あの近辺を旅行に行ったんです」とおっしゃる生徒さんがいらっしゃいました。「そうでしたか。能登は朝市とかも有名ですしね」と申しますと、「ちょっと思い入れがあったものですから、今回の地震や津波で大きな被害が出てしまって、本当にショックで…」と、大変残念そうな表情でお話をされていました。一日でも早い復旧と復興を願わずにはいられません。
震災の話の後も、いろいろなお話をしました。
奥様に、「定年を迎えて、時間もある事だし、英語とかピアノとかやったら?」と言われたことがきっかけで入会された生徒さんは、レッスン前にお教室をレンタルして、直前まで熱心に練習をされる方です。そんな生徒さんですが、今週のレッスンでは、「今回、実はあまり練習していなくて。すみません」とおっしゃるので少し驚きました。「そうなのですね。お忙しかったようですね。そういう事もありますから。あまり気にされずに、どうぞ気兼ねなくレッスンにいらして下さいね」とお返事をしました。
すると、「いや~、ありがとうございます。実は、先日ゴルフをしに行きまして…」と話し始めました。「へえ~、ゴルフをされているんですね」。「前に話したと思いますが、僕は学生時代にラグビーをやっていて、その時のメンバーで年に何回かゴルフをやるんです。今回は16人だったかな?そのくらい集まって」。「学生時代にラグビーをやっていたお仲間で、今はゴルフをされているなんて凄いですね」。「いや~、ホントに楽しかったですよ!みんないろんなことをやっているんで。商社にいた人もいれば、警察官もいて」。「一緒にラグビーをやっていた方々が、その後いろいろな業界でお仕事をされていたなんて面白いですね」。「ホント、そうなんですよね。医者もいるし、スポーツ庁の人もいるし、弁護士もいるし」。「すごく幅広いジャンルで、みなさんご活躍なんですね。そういう方々と繋がりがあって、なんだか羨ましいです」とお話が弾みました。
ピアノを専門にしていますと、基本的に個人プレーなので、みんなで何かをするという機会がかなり少ない気がしています。他の楽器ですと、室内楽やオーケストラで他の方々との共演という機会もあるのでしょうが、ピアノの場合、あったとしても連弾や他の楽器の伴奏という事がほとんどなので、2人で演奏するくらいしか機会がないように思います。また、例えばピアノ講師のような職業の場合、ほとんどが音楽大学を卒業しているのですが、音楽大学は単科大学なので、他の学部や学科がありません。みんな音楽を学んでいて、学んでいる楽器が異なるだけという事になります。しかし、この生徒さんの場合は、同じ大学で一緒にラグビーをやっていたメンバーですが、専門は文学部だったり経済学部だったりと、いろいろな分野の方々が集まっているという事なのですね。
音大を卒業した後の進路は、大雑把に言えばプロの演奏家になるか、音楽教室や学校などの音楽の指導者になるかという2つに限られてきます。もちろん、全く異なる業界でお仕事をされる方もいますが、少数派という印象です。つまり、卒業後も同じような業界に携わっていることが多く、代り映えしないとも言えます。そのため、生徒さんのお話を聞いて、「みんなで、何か同じ一つの事をするという体験が少なかったなあ」という思いと、単純に「楽しいそうで良いなあ」という気持ちになります。それと同時に、ピアノのレッスンにいらしている方々は、様々な業界に携わっているので、レッスンを通して、私自身も視野が広がり、いろいろな業界を知る事が出来て、生徒さん方から多くの事を学ばせていただいているとも感じています。これからも、生徒さん方との出会いに感謝しつつ、充実したレッスンを展開していきたいと思っています。
小学生の生徒さん方は、年末年始のお休みも終わり、学校では新学期を迎えています。新学期早々から、何となく少し元気のない様子を見せている生徒さんもいて、「どうしたの。大丈夫?」と声をかけますと、「だって…、明日から5時間授業だし、その次は、もう6時間授業になっちゃうんだよ」と、この先の学校の授業時間の長さについて心配をしていました。「あら、大変ね。学校が始まったら、直ぐに元通りのスケジュールになっちゃうのね。今週1週間は、長く感じちゃいそうだけど頑張ろうね」と励ましました。
ピアノの教材を広げて準備をしている時に、「この曲は、今日からレッスンをする新しい曲だけど、譜読みをしてみてどうだった?」と聞きますと、「ここまで弾けたよ。お父さんが、この曲を小さい頃に弾いたことがあるって言っていて、弾いてくれたよ。でもね、この小節の指番号が難しくて、お父さんは弾けなかったよ。私は、弾けるようになったけれどね」と、ニコニコしながら話してくれました。「そうなのね、お母様だけでなく、お父様もピアノが弾けるのね。お父様が弾けなかったところが、〇〇ちゃんは弾けたって凄いじゃない。お父様を超えたね」と話しますと、笑いながら、「うん、そうだね!」と嬉しそうに答えてくれました。
昨年の春からピアノを習い始めた保育園生の生徒さんは、少し前から、ワークが出来た時やピアノの曲が弾けるようになった時に、合格という意味で私が書いている花丸を、自分で書くことがマイブームになっています。年明けのレッスンでも、以前弾けるようになった楽譜を広げては、花丸ではなく「なると」と言い、そして「〇〇ちゃん(自分の事)ね、ラーメンのなるとが大好きなの」と話を続けるのが定番になっています。この日も、ワークがしっかりと出来ていたので、私が花丸を書こうとしますと、直ぐに、「〇〇ちゃん(自分の事)が書く~」と言って赤ペンを取り出し、小さめにぐるぐると渦巻きを書き、周りに曲線を描いて、「なると~」と言いながら、休み明けのレッスンで嬉しかったのか、なるとを4個もニコニコしながら書いていて、切り上げさせるのに少し苦労しました。
最近ピアノで弾けるようになった「メリーさんの羊」という曲がお気に入りのようで、「〇〇ちゃん(自分の事)ね、メリーさんの羊、楽譜を見なくても弾けるよ」と、自信満々で楽しそうに弾いていました。今年は、初めてピアノの発表会に参加する予定ですが、暗譜の心配もなさそうですし、楽しそうに自信を持って弾いている姿も頼もしく、この調子で進められたら、初舞台での演奏もきっと成功できるだろうなあと思っています。これから先の成長が、楽しみです。
今年も、生徒さん方それぞれがご自分のペースで楽しく、そして上達できるように、精一杯レッスンを行っていきたいと思っています。
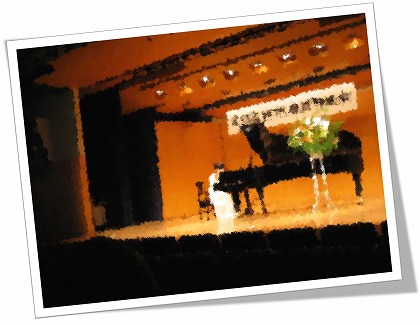
(この記事は、2023年11月6日に配信しました第384号のメールマガジンに掲載されたものです)
今回は、大人の生徒さんの発表会のお話です。
先日、大人の生徒さんの発表会が行われました。発表会は近年、コロナの影響で中止になったり、1回あたりの参加人数をかなり少なくして開催してきましたが、今回は、コロナ前とほぼ同様な形で行われました。参加人数は従来通りとなり、観客の人数も制限を設けず、集合写真も復活、講師演奏も行われました。
当日、開場時間前に、関係する講師やスタッフとの打ち合わせを行いました。発表会の進行の確認や、欠席連絡、演奏曲目などの確認のほか、今回はヴァイオリンの人達との合同発表会でしたので、ヴァイオリンの生徒さんの演奏する立ち位置や譜面台の設置場所の確認、ピアノ伴奏の際の屋根の開閉の確認なども行いました。
「屋根」とは、グランドピアノの弦が張ってある部分の蓋のことで、レッスンでは部屋が狭いこともあり、閉めたまま弾くことが多いと思いますが、発表会やリサイタルなどでは、通常大きく開けて演奏します。しかし、発表会でも、他の楽器や声楽の伴奏としてピアノを使用する場合は、音量のバランスを考えて少し開けるくらいで演奏します。ちなみに、2台ピアノの演奏時には、ピアノを向かい合わせに設置しますが、この状態で2台のピアノ共に屋根を全開にしてしまうと、客席に近い方のピアノ(演奏者が舞台向かって右側に座る)の蓋が客席とは反対側に開き、客席から見まると壁のようになってしまいますので、こちらのピアノの屋根は取って演奏します。
打ち合わせ後、出演される生徒さんにご挨拶をしました。いつもご夫婦で開場前からいらしている生徒さんは、今回はお一人で来られていました。「あれっ」と思いましたが、「いよいよですね。調子はいかがですか?」と声を掛けますと、「親戚が亡くなりまして…」とお話になりました。実は前日のレッスン時に、「以前から親戚の容体が悪く、今日明日に何かあっても不思議ではない」というお話はされていました。「それでも、ピアノの発表会だけは参加しようと思っています」と大変な状況にも拘わらず、ピアノの発表会をやり遂げるという固い決意を感じて、ご立派だなあと感じました。
「何かありましたら、遠慮なくいつでもご連絡を下さい」とお話をしましたが、その後連絡がなかったので、てっきり容体が少し安定したのかなと思っていたので、私も大変驚き、「まあ…、そうでしたか…」としか言葉がかけられませんでした。「ピアノは、相変わらず間違いだらけですが頑張ります」と、気丈に振舞われていて、やはり凄いなあと思いました。
別の大人の生徒さんは、早い時間から音出し用のレッスン室で、最後の練習を熱心にされていました。区切りの良さそうなところで、「調子はいかがですか?1回聴かせてください」と声を掛けて、本番前に演奏の確認をしました。1ヵ月前くらいに、本番の譜めくりについてお話をしたところ、「2ページ目以降は暗譜できているからいいんだけど、なにしろ1ページ目の特に最初の方が、なんか覚えにくいんだよね。何回弾いても、覚えられないんだよね」とお話されていました。
大人の生徒さんの発表会では、暗譜は自由という事になっていますので、楽譜を見て弾かれる方が圧倒的に多くなります。この生徒さんは、ほとんど暗譜で弾いているのですが、発表会では、「楽譜は譜面台に置いても見ないから、ほとんど関係ないんだけれどね」とおっしゃりつつ、念のため楽譜を置くことにしています。今回は、1ページ目の暗譜が多少不安という事もあり、楽譜を見て弾く事にしました。
暗譜が心配とお話されていた、1ページ部分は、楽譜を見て弾いているので、何の音を弾くのかわからなくなるという事はなく弾けていました。2ページ目以降も、だいぶスムーズで調子が良さそうでしたが、最後のページの中頃で左手の音が1つ抜けてしまい、その動揺も影響したのか、最後の3小節手前部分で、なんと演奏する手が違っているという事がありました。この箇所は、レッスンでは一番最初の譜読みの時以外は間違えたことがないくらいに、安定感抜群に弾ける所でしたが、本番直前にまさかの事態に、私の方が内心動揺してしまいました。生徒さんご自身は、「えっ?違った?」とケロッとされていたのが幸いでしたが。
そして、会場に移動しますと、なんとほぼ満席状態です。このような光景は、久しぶりでしたので嬉しく思いました。受付のスタッフの方も、「今回は本当にお客様が多くて」と驚いていました。
前半は、ヴァイオリンの生徒さんのステージで、ピアノ伴奏付きの他、先生とのヴァイオリン2重奏もありました。大変スムーズに進行していて、予定時間ピッタリに前半が終わり、休憩後にピアノの生徒さんのステージへ移りました。
ご親戚が当日朝に他界された生徒さんは、舞台上では一切動揺がなく、普段通りに演奏されていました。レッスンでお話をしていた、大きなフレーズが終わったらしっかりとブレスを取るという事が、本番でも自然にできていて、とても歌心のある演奏をされていました。
1ページ目が覚えにくいとお話されていた生徒さんは、問題の1ページ目で少し調子を崩してしまいましたが、その後は体制を整えて演奏ができ、本番直前に弾く手を間違えていたところも、元通りに演奏でき、無事に最後まで弾ききることができました。
今回は、80代の生徒さんも何人か参加されていたようですが、その中のお一人が、かなり緊張してしまったのか、冒頭部分でかなり手こずってしまい、その後も動揺が影響してしまったのか、普段の力が発揮できないまま終わってしまいました。大人の発表会の場合、稀にそのような事が起きるのですが、そのような時にどう対応するのがベストなのか、改めて考えさせられました。自力で音楽を先に進めることができれば、それに越したことはないのですが、なかなか思うようにいかないことが多いものです。緊張して、一音抜けてしまった、指番号を間違えたなど、きっかけは些細な事なのですが、それで調子を崩してしまい影響が大きくなってしまいます。
この生徒さんは、楽譜を覗き込みながら何回も弾き直していましたが、どこの音が間違えていて、本当は何の音を弾くべきなのか、わかっていない様に見えました。このような間違いにはまってしまいますと、なかなか立て直せないものですが、この生徒さんは、その後なんとか次には進め、しかし、また途中で同じような事が起こっていました。2曲目では、少し調子が戻って来たようでしたが、残念ながら本来の力が発揮できなかったように見えました。
あからさまに、舞台に駆け上がって、「この音ではなく、こちらの音ですから、この鍵盤を弾いてくださいね」などと助けるのも、いかがなものかとも思いますし、生徒さんによっては快く思わないでしょう。しかし、「一度舞台に上がったら、お手伝いは出来ませんので、自力で何とかしてください」という対応も、大人の生徒さんの発表会でふさわしいのか疑問にも思います。
この生徒さんは、終演後に集合写真の撮影があったのですが、「思うように全然弾けなかったから、帰ります」と写真撮影前に、お帰りになってしまいました。よほど心残りの演奏になってしまったようで、私も何か気の利いた言葉をかけて差し上げられなかったことを残念に思いました。
普段のレッスンでも、緊張して間違えたりしても、なんとか最後まで弾ききる対策として、繰り返し部分や大きな場面転換のところなど、曲の途中から弾く練習をしたり、本番で弾いているような気持ちで、間違えても、とにかく最後まで止まらずに弾く練習を、ご自宅でもチャレンジするようにお話をしています。
曲の最初からでないと弾けないという方は、結構多いですし、弾いていて「あれっ?」と思った瞬間に指が止まる方も、ちらほら見受けられます。もし、思い当たる方は、上記のような練習をしてみますと、「意外にできるから自信を持とう」とか「案外難しい。もっと練習しよう」とか、ご自身の演奏の新たな発見があるかもしれません。
今回の発表会では、本番で想定外のアクシデントが起きた場合の対応について、生徒さん自身の力で先に進めそうか、どの段階で判断するのか、助けが必要と判断した場合、どのようにしたら、さり気なくサポートができるのか、そもそも防止するために普段からどのような準備をしておくとよいのかなど、改めて見直すきっかけにもなりました。力が発揮できなかった生徒さんが、なんとか今回の件を乗り越えて、次回また参加されることを切に願っています。
最近の投稿
- お子様のピアノ発表会
- 世界を視野に入れ活躍する超新星
- お子様の発表会に向けた練習
- ベートーヴェンがベートーヴェンになった瞬間
- 春のお子様の生徒さんの様子
- ベートーヴェンが作曲家になる過程
- ヘンデルのお話
- 新しいクラシック
- どうぶつとクラシック
- オーケストラの日
カテゴリー
ブログ内検索
メールマガジン
音楽ナビ
con Vivace について
アーカイブ
- 2025年9月 (1)
- 2025年8月 (1)
- 2025年7月 (2)
- 2025年6月 (3)
- 2025年5月 (2)
- 2025年4月 (2)
- 2025年3月 (2)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (3)
- 2024年11月 (2)
- 2024年10月 (2)
- 2024年9月 (2)
- 2024年8月 (2)
- 2024年7月 (2)
- 2024年6月 (2)
- 2024年5月 (2)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (2)
- 2024年2月 (2)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (2)
- 2023年9月 (2)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (2)
- 2023年5月 (2)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (2)
- 2023年2月 (2)
- 2023年1月 (1)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (3)
- 2022年9月 (2)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (1)
- 2022年6月 (2)
- 2022年5月 (3)
- 2022年4月 (2)
- 2022年3月 (2)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (1)
- 2021年12月 (3)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (2)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (2)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (2)
- 2021年3月 (3)
- 2021年2月 (1)
- 2021年1月 (3)
- 2020年12月 (3)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2020年9月 (2)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (2)
- 2020年6月 (2)
- 2020年5月 (2)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (3)
- 2020年2月 (2)
- 2020年1月 (2)
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (2)
- 2019年10月 (2)
- 2019年9月 (3)
- 2019年8月 (1)
- 2019年7月 (2)
- 2019年6月 (2)
- 2019年5月 (2)
- 2019年4月 (2)
- 2019年3月 (3)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (2)
- 2018年12月 (3)
- 2018年11月 (2)
- 2018年10月 (3)
- 2018年9月 (2)
- 2018年8月 (2)
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (2)
- 2018年5月 (2)
- 2018年4月 (3)
- 2018年3月 (2)
- 2018年2月 (2)
- 2018年1月 (2)
- 2017年12月 (3)
- 2017年11月 (2)
- 2017年10月 (3)
- 2017年9月 (2)
- 2017年8月 (2)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (2)
- 2017年5月 (3)
- 2017年4月 (2)
- 2017年3月 (2)
- 2017年2月 (2)
- 2017年1月 (2)
- 2016年12月 (3)
- 2016年11月 (2)
- 2016年10月 (2)
- 2016年9月 (1)
- 2016年8月 (2)
- 2016年7月 (3)
- 2016年6月 (2)
- 2016年5月 (2)
- 2016年4月 (2)
- 2016年3月 (2)
- 2016年2月 (2)
- 2016年1月 (5)
- 2015年12月 (2)
- 2015年11月 (1)
- 2015年10月 (3)
- 2015年9月 (2)
- 2015年8月 (2)
- 2015年7月 (2)
- 2015年6月 (3)
- 2015年5月 (3)
- 2015年4月 (2)
- 2015年3月 (2)
- 2015年2月 (2)
- 2015年1月 (5)
- 2014年12月 (3)
- 2014年11月 (2)
- 2014年10月 (3)
- 2014年9月 (3)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (4)
- 2014年6月 (2)
- 2014年5月 (3)
- 2014年4月 (3)
- 2014年3月 (4)
- 2014年2月 (2)
- 2014年1月 (4)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (2)
- 2013年10月 (5)
- 2013年9月 (3)
- 2013年8月 (2)
- 2013年7月 (2)
- 2013年6月 (2)
- 2013年5月 (3)
- 2013年4月 (4)
- 2013年3月 (3)
- 2013年2月 (2)
- 2013年1月 (4)
- 2012年12月 (3)
- 2012年11月 (4)
- 2012年10月 (1)
- 2012年9月 (2)
- 2012年8月 (3)
- 2012年7月 (4)
- 2012年6月 (5)
- 2012年5月 (4)
- 2012年4月 (4)
- 2012年3月 (5)
- 2012年2月 (4)
- 2012年1月 (6)
- 2011年12月 (5)
- 2011年11月 (3)
- 2011年10月 (3)
- 2011年9月 (2)
- 2011年8月 (2)
- 2011年7月 (4)
- 2011年6月 (2)
- 2011年5月 (3)
- 2011年4月 (2)
- 2011年3月 (3)
- 2011年2月 (3)
- 2011年1月 (4)
- 2010年12月 (4)
- 2010年11月 (2)
- 2010年10月 (4)
- 2010年9月 (1)
- 2010年8月 (4)
- 2010年7月 (3)
- 2010年6月 (54)
