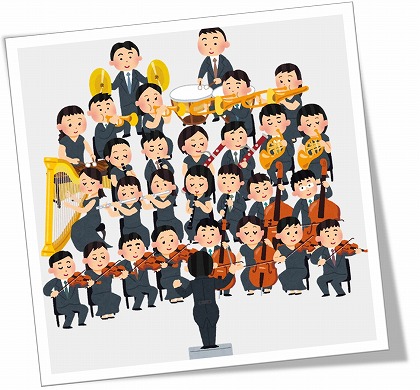
(この記事は、2025年2月24日に配信しました第416号のメールマガジンに掲載されたものです)
今回は、指揮者による音楽の違いについてのお話です。
長く音楽に携わていますと、ちょっとでも音楽が聞えてくると「何の曲だろう?」と気になり、耳を傾けて演奏に聞き入ってしまったり、演奏の仕方が気になってしまいます。生身の人間が演奏していないものについては、違和感を感じるので特に気になります。駅へ行きますと、電車の発車メロディーが流れますが、勝手に頭の中で音を聞き取り、楽譜に書き起こしてしまう事も多々あります。
また、アレンジされている曲が流れていると、「えっ、そこでここに飛んじゃう?」とか「ここ、カットしちゃうのね」など、いろいろ思う事もあります。そのため、よく受験生がBGMを流しながら勉強していますが、私の場合は、ついつい音楽の方に耳が吸い寄せられてしまうので、勉強が全然はかどりませんでした。
もっとしっかりと絶対音感が付いている方は、あらゆる音が、ドレミ…で聴こえるそうで、私以上に気が休まらないのではないかと思います。もちろん、音楽にフォーカスしないように、耳のスイッチを自分でオンオフすることができるようになってきますがね。
先日、『なぜ、クラシック音楽ファンは「誰が指揮するか」をやたら気にするのか』という記事を目にしたので、読んでみました。
ピアノ教室にいらしている生徒さん方は、音楽好きな方々なので、ご自宅でピアノの練習をするだけではなく、普段からいろいろと音楽との接点が多いように見受けられます。ピアノ以外の楽器やコーラスをされていたり、音楽系のテレビ番組を見ていたり、リサイタルやコンサートに足を運んだり、音楽系がテーマの映画を見たり本を読んだりされています。
その中で、交響楽団の会員になっている生徒さんは、この記事の通り、「この前行ったコンサートは、〇〇が指揮をしていて…」と、誰が指揮をするのかチェックして演奏会を選んでいるようです。
この記事の「交響曲は指揮者次第?」という項目では、クラシック音楽は、演奏家が異なると、全く違う様に聴こえることがままあると述べられています。これは、ピアノなど楽器を演奏している方は、直ぐにピンとくると思います。ピアノのレッスンにいらしている生徒さん方でも、新しく練習する曲を決めるときに、YouTube などでプロの演奏家の演奏を聴いて、「あ~素敵っ!これを弾いてみたい」と思い練習を始める方がいらっしゃいます。
練習を始めて最初の頃は、無我夢中で音を読んでピアノを弾きますが、ご自分が何の曲を弾いているのかよくわからないという方も少なくないようです。先日も、とても有名なピアノ曲を練習している生徒さんが、「まだまだ、音楽が聴けてこないです」とおっしゃっていました。ご自分が良いと思って選んだ曲を弾くわけですが、どうも同じ曲に聴こえない、まさに演奏者によって違ったように聴こえるという事ですね。
私自身も、先日生徒としてピアノのレッスンを受けた時に、先生が弾くフレーズが、つい先程自分が弾いたフレーズと全く異なっていて、先生の演奏の素晴らしさを感じつつ、自分の実力を思い知らされて複雑な思いをしました。
オーケストラも、指揮者の存在が大きく、同じオーケストラでも指揮者次第で素晴らしかったり、そうでなかったりと、ものすごい差が生まれると書かれています。記事の中で、極端な例として、ブルックナーの「交響曲第8番」について述べられていました。ブルックナーの傑作なのですが、指揮者によって70分くらいで演奏されることもあれば、100分かけて演奏されることもあるそうなのです。演奏時間が30分も異なると、だいぶ曲の印象が変わりそうですね。
筆者の音楽評論家 許光俊さんがご自身の経験を語っていて、最初に買ったレコードがカラヤン指揮のもので、子供ながらに違和感を感じたそうですが、その後で買ったベームが指揮をした音楽は圧倒的にしっくりきたそうです。後に、カラヤンの指揮が、表面的とか機械的という批判があることを知って、「そうだ」と膝を打ったことが書かれていました。
ショパンコンクールが開催されていた時、生徒さん方に、「YouTube の公式チャンネルで、コンクールの演奏が聴けるので、ご興味があれば聴いてみて下さいね」とお話したところ、早速聴いた生徒さんが、「同じ曲でも、弾く人によって、とても違っていて驚いた」と感想を話されていました。
私も、ちょうどショパンの曲を練習していたこともあり、いつにも増して興味津々で聴いたのですが、とにかく速いテンポで弾く方がとても多く、ゆっくりのテンポの曲はとってもゆっくり弾いていることも多々あり、本当にこんなテンポで弾くのかと驚いて、ピアノの先生に聞いたものです。その先生は、「コンクールだから、速く弾いた方がやはり華やかさが出るし、テクニックもアピールできるし、印象に残るんじゃない?また、他の曲との対比などを考えてテンポ設定をしているかも」と話していました。
その時に、私が、「みなさん、とにかく速く弾いていてびっくりしましたが、〇〇さんの演奏は、私が思っているテンポで弾いていて、そうそう、これこれ!という感じで、すごく納得したのですが…」とお話したところ、「そうね、とてもきれいに弾いていてリサイタルだと良いのかも知れないけれど、コンクールの場だと、ちょっと地味に聴こえちゃうのよね」とも話していて、なるほどコンクールという他者との比較の場だと、いつもとは異なる演奏になるのかもしれないと思ったものです。
同じ演奏者でも、年月を経て何回も同じ曲を録音していることがありますが、昔の解釈と今の解釈が異なることもあり、おのずと演奏も変わってくるのでしょう。
「決定版 交響曲の名曲・名演奏」という本の中で、この記事の筆者である許さんが書いていますが、「だれだれ指揮のどこそこ管弦楽団との演奏」と記してはいても、何年の録音とかは、あえて記していないそうです。どの録音かが書いてあると印象がどうなるか、自分で考えながら自分の耳で音楽を聴くことが大事なんだそうです。
近年は、演奏会に足を運べなくても、いろいろな方法で身近に音楽を聴くことができるようになっていますので、私も、指揮者にもっと注目をしながら、やはりブルックナーの交響曲第8番を聴き比べてみたいと思います。
最近の投稿
- 大人の生徒さん方の様子
- 指揮者による音楽の違い
- 早春のピアノ教室
- 年明けのピアノ教室
- 2025年メモリアルイヤーの作曲家
- 日本音楽コンクールの話
- 町田樹が語るショパン
- クラシック音楽を支えるプロフェッショナルたち
- 晩秋のピアノ教室
- 3か月でマスターするピアノ
カテゴリー
ブログ内検索
メールマガジン
音楽ナビ
con Vivace について
アーカイブ
- 2025年3月 (2)
- 2025年2月 (2)
- 2025年1月 (1)
- 2024年12月 (3)
- 2024年11月 (2)
- 2024年10月 (2)
- 2024年9月 (2)
- 2024年8月 (2)
- 2024年7月 (2)
- 2024年6月 (2)
- 2024年5月 (2)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (2)
- 2024年2月 (2)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (2)
- 2023年9月 (2)
- 2023年8月 (2)
- 2023年7月 (2)
- 2023年6月 (2)
- 2023年5月 (2)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (2)
- 2023年2月 (2)
- 2023年1月 (1)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (3)
- 2022年9月 (2)
- 2022年8月 (2)
- 2022年7月 (1)
- 2022年6月 (2)
- 2022年5月 (3)
- 2022年4月 (2)
- 2022年3月 (2)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (1)
- 2021年12月 (3)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (2)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (2)
- 2021年6月 (2)
- 2021年5月 (2)
- 2021年4月 (2)
- 2021年3月 (3)
- 2021年2月 (1)
- 2021年1月 (3)
- 2020年12月 (3)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (2)
- 2020年9月 (2)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (2)
- 2020年6月 (2)
- 2020年5月 (2)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (3)
- 2020年2月 (2)
- 2020年1月 (2)
- 2019年12月 (2)
- 2019年11月 (2)
- 2019年10月 (2)
- 2019年9月 (3)
- 2019年8月 (1)
- 2019年7月 (2)
- 2019年6月 (2)
- 2019年5月 (2)
- 2019年4月 (2)
- 2019年3月 (3)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (2)
- 2018年12月 (3)
- 2018年11月 (2)
- 2018年10月 (3)
- 2018年9月 (2)
- 2018年8月 (2)
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (2)
- 2018年5月 (2)
- 2018年4月 (3)
- 2018年3月 (2)
- 2018年2月 (2)
- 2018年1月 (2)
- 2017年12月 (3)
- 2017年11月 (2)
- 2017年10月 (3)
- 2017年9月 (2)
- 2017年8月 (2)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (2)
- 2017年5月 (3)
- 2017年4月 (2)
- 2017年3月 (2)
- 2017年2月 (2)
- 2017年1月 (2)
- 2016年12月 (3)
- 2016年11月 (2)
- 2016年10月 (2)
- 2016年9月 (1)
- 2016年8月 (2)
- 2016年7月 (3)
- 2016年6月 (2)
- 2016年5月 (2)
- 2016年4月 (2)
- 2016年3月 (2)
- 2016年2月 (2)
- 2016年1月 (5)
- 2015年12月 (2)
- 2015年11月 (1)
- 2015年10月 (3)
- 2015年9月 (2)
- 2015年8月 (2)
- 2015年7月 (2)
- 2015年6月 (3)
- 2015年5月 (3)
- 2015年4月 (2)
- 2015年3月 (2)
- 2015年2月 (2)
- 2015年1月 (5)
- 2014年12月 (3)
- 2014年11月 (2)
- 2014年10月 (3)
- 2014年9月 (3)
- 2014年8月 (1)
- 2014年7月 (4)
- 2014年6月 (2)
- 2014年5月 (3)
- 2014年4月 (3)
- 2014年3月 (4)
- 2014年2月 (2)
- 2014年1月 (4)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (2)
- 2013年10月 (5)
- 2013年9月 (3)
- 2013年8月 (2)
- 2013年7月 (2)
- 2013年6月 (2)
- 2013年5月 (3)
- 2013年4月 (4)
- 2013年3月 (3)
- 2013年2月 (2)
- 2013年1月 (4)
- 2012年12月 (3)
- 2012年11月 (4)
- 2012年10月 (1)
- 2012年9月 (2)
- 2012年8月 (3)
- 2012年7月 (4)
- 2012年6月 (5)
- 2012年5月 (4)
- 2012年4月 (4)
- 2012年3月 (5)
- 2012年2月 (4)
- 2012年1月 (6)
- 2011年12月 (5)
- 2011年11月 (3)
- 2011年10月 (3)
- 2011年9月 (2)
- 2011年8月 (2)
- 2011年7月 (4)
- 2011年6月 (2)
- 2011年5月 (3)
- 2011年4月 (2)
- 2011年3月 (3)
- 2011年2月 (3)
- 2011年1月 (4)
- 2010年12月 (4)
- 2010年11月 (2)
- 2010年10月 (4)
- 2010年9月 (1)
- 2010年8月 (4)
- 2010年7月 (3)
- 2010年6月 (54)
